安かろう悪かろうと無視できる存在では無くなった中国製のストロボ。その中でも日本での知名度・クオリティの高さではGODOXが頭一つ抜けていると思います。
モノブロックストロボはProfoto D1を使っていましたが、修理する場合は内容によっては数万円かかります。
GODOX AD400 Proは400Wの大光量、バッテリー式でチャージも早い。さらに別売りのオプションでAC電源仕様でも使え、Profotoのアクセサリー類も使用でき、10万円を切る価格で買えるという驚きのコストパフォーマンスの高さです。
スペックだけ見れば、Profotoの高価なストロボとも遜色ないGODOXのストロボ。購入し実際に仕事の撮影で使用してみた上で、Profoto D1と比較しながらレビューしてみたいと思います。
外観
以下、左がGODOX AD400 Pro、右がProfoto D1です。

発光部正面
正面から見た図です。GODOXにはProfoto用アダプターを装着しています。
発光管はどちらもC型の円形のものですが、Profotoの方が一回り大きいです。
どちらも前面はすりガラスになっており、GODOXの方がやや透け感が少ないです。

スタンドとの接合部
両方ともスタンドとの接合部は金属製のしっかりしたもので、メス仕様です。
ヘッド調整のノブはどちらもプラスチックのような素材ですが、しっかりした作りです。
Profotoはヘッドの動きがやや硬く、ノブを締めるとしっかり止まります。大型で重量のあるソフトボックスなどを取り付けたときにもきっちり止まります。
GODOXの方はやや緩く、重いソフトボックスなどを取り付けたときは、かなりの力でノブを締めないとヘッドが動いてしまいます。

操作部
Profotoの方がシンプルで直感的な操作が出来ます。
GODOXはビープ音のオンオフの設定にメニューから何階層か進まないといけなかったりと、メニューが複雑な部分があり、急いでいるときに操作感で不満を感じることがあります。
選択に使う回転式のダイヤルもProfotoの方が回し易く使い勝手が良いです。
ボタンの質感や押しやすさなどはProfotoが勝っています。
使用感
ズーム機能の比較
Profotoの特徴であるズーム機能を比較してみました。
装着したのはズームリフレクター(旧型)です。

ズームリフレクターを装着した状態。
Profotoのアクセサリ類をGODOX AD400 Proに装着するには別売のアダプターが必要です。

↑GODOX AD400 Pro
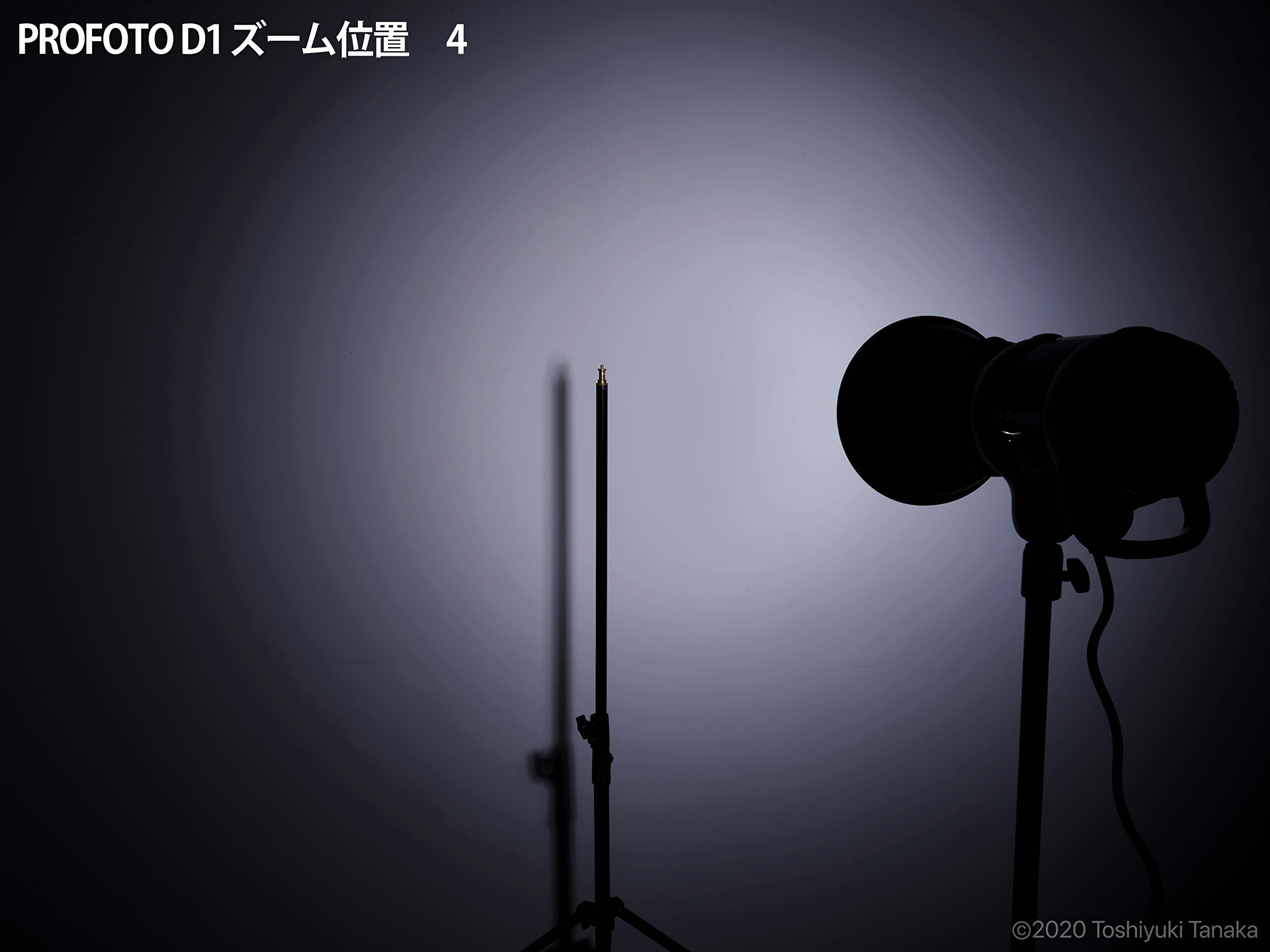
↑Profoto D1
両方ともズーム位置4と6では似たような光の拡がり方です。
リフレクターを一番奥のポジションに装着したとき、ズーム部分の全長の違いのためか、光の拡がり方に差が出ます。Profoto D1は光の芯がほぼ見られず、全体的に均一に拡散しています。GODOXは一番奥でも芯が残り、Profotoのように均一には広がらないです。
参考までにProヘッドにズームリフレクターを装着したものが以下です。
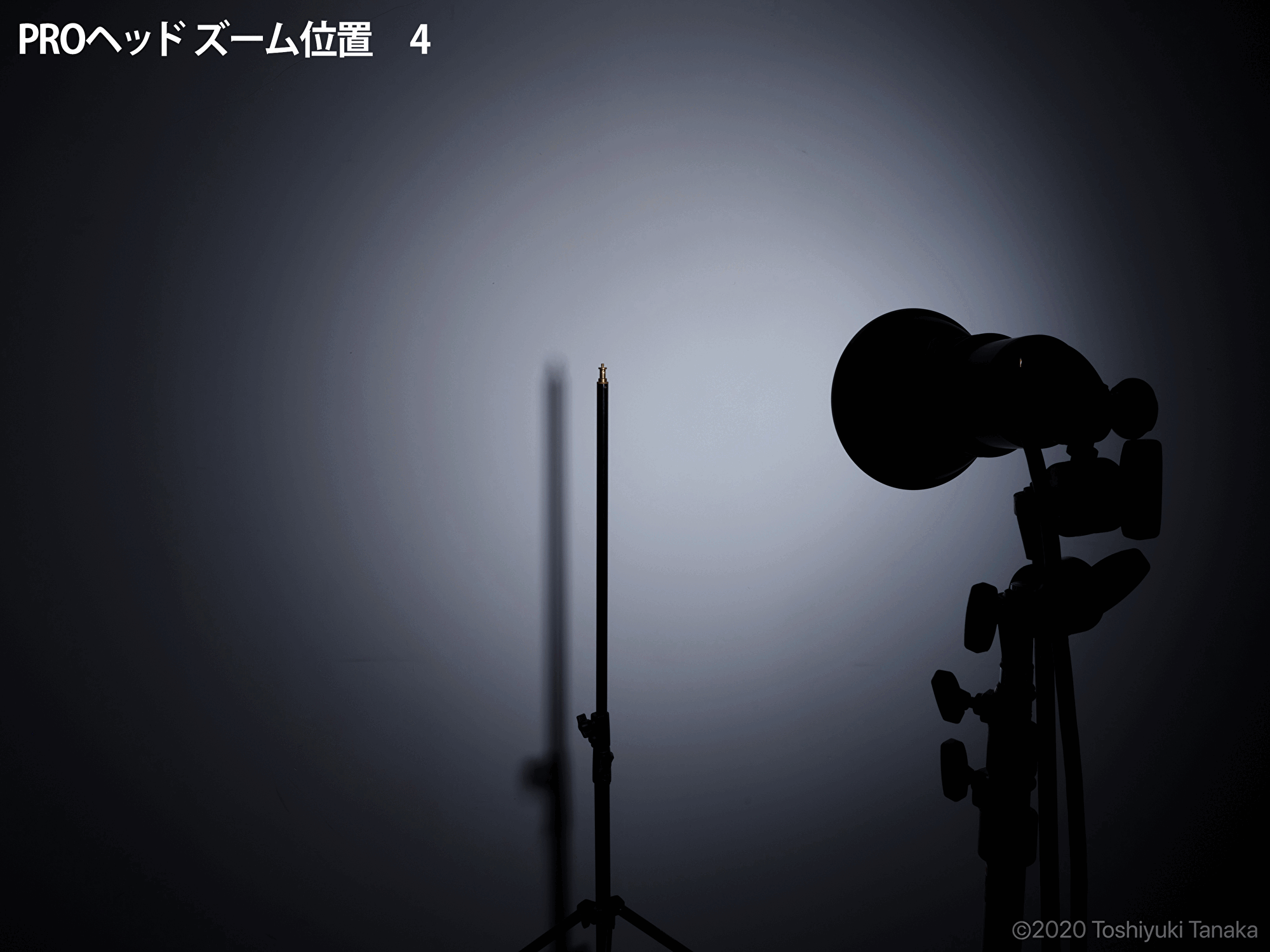
モノブロックストロボ2種類と比べ、ズーム位置4と6での変化が顕著です。一番奥にしたときの光の均一性もProヘッドが一番です。
光の色について
ズームリフレクターの比較写真でも分かるように、GODOX AD400 ProはProfoto D1よりも青っぽい色味です。
同じメーカー・機種でも発光管の劣化度合いなどの様々な要因で個体差はあります。しかし、上の写真で見る限り、ProヘッドとD1の色味の傾向は比較的近いので、Profotoではある程度ちゃんと一貫性を持って作られていると思います。


どちらもカメラのWB設定を太陽光にしてそのまま現像しています。GODOXの方は青っぽくProfotoは若干の赤みがあります。
これらのストロボを混在して使用するときには、色味の違いに気をつけて使ったほうが良さそうです。
リモートコマンダー

Profotoの方はD1購入時に付属していた、Air Remoteを使用しています。現在はストロボ購入時には付属しておらず別途購入する必要があり、4万円以上します。TTL・HSSなどは使えず、無線での発光と出力の調整、ヘッド・モデリングランプのオンオフのみと機能が絞られています。D1にはTTLなどの機能は無いので、こちらで必要充分ですが、TTLやHSSの機能があるProfotoのストロボでそれらの機能を使いたい場合はより高額なAir Remote TTLが必要です。
コマンダーには液晶画面がないので、ストロボの出力の上げ下げは出来ても、現在のストロボの出力がいくつになっているかはストロボ本体でしか確認できません。
GODOX AD400 proではXproというコマンダーを使用しています。こちらは1万円を切る価格で、TTL・HSSなどの機能も使用可能です(Xproは後幕シンクロが出来ません。どうしても後幕シンクロが使いたい場面があり追加でX2Tというコマンダーも購入しました。値段はX2Tの方が少し安いですが、操作性などはXproの方がはるかに良いので、後幕シンクロが必要でないならXproの方がオススメです)。大きめの液晶がついており、ストロボの出力やメニューが表示でき、操作が分かりやすいです。
Xproは本体側面にコマンダーのオンオフスイッチがついているのですが、スイッチが緩くバッグの中などで勝手にオンになっていて電池が切れてしまっているときがあります。Air Remoteはスイッチ長押しで電源が入るので、そういった心配は少ないです。
両方とも発光ミスもなく、安定して使用できます。Profotoは単4、GODOXは単3電池を使用するのですが、電池持ちも良いです。
他社ストロボとの併用について追記(2021.5.4)
ProfotoとGODOXのストロボを併用する方法についてコメントでご質問を頂いたので、軽く実験してみました。
コメントでは3つの方法を挙げさせて頂いたのですが、それらについて書きたいと思います。
1つ目は光学式のスレーブ機能を使う方法です。

AD400 Proは本体上部に受信部があります。この部分で他のストロボの光に反応しストロボを発光させます。

メニューのSLAVEという項目からON・OFFを切り替えられます。S1・S2とあるのですがこれがどういった機能なのかは説明書を見ても分かりませんでした…
とりあえず、S1に設定すれば他のストロボと同調して発光します。
この光学式スレーブは他の機材なども必要なく、手軽に使える反面いくつか問題点もあります。
- 一つの空間で、複数の撮影セットを組んでいる場合
→他のセットの発光に反応してしまうことがあります。 - ストロボの配置によってスレーブ受信部に他のストロボの光が届かない場合
→スレーブの受信感度は良いほうだとは思うのですが、それでも受信部に光が届かない場合があるので、ストロボの配置などに制限が出る可能性があります。
2つ目は上でもご紹介した、X2Tというコマンダーを使用する方法です。

X2Tにはコマンダー上部にホットシューがあるので、そこに他のリモートコマンダーを重ね付けすることが可能です。
コメントを頂いた際に、発光が不安定だったと返信したのですが、気になって少し実験してみました。
動画では10回発光させていますが、その後100回ほど実験してみたところすべて問題なく、両方のストロボが光っていました。
この方法だとGODOX・Profotoの両方のストロボの出力などをカメラにつけたリモートコマンダーで操作することが出来ます。見た目は仰々しくなってしまうのですが、併用する方法としては操作性を損なわずにスマートに使えると思います。
1つ欠点があり、X2Tに重ねづけしている方のコマンダーではHSSやTTLなどは使えませんでした。
ただ、そこを差し引いてもGODOXとProfotoを併用したいときにはベターな方法かと思います。
3つ目はシンクロソケットを使う方法です。
AD400 Proは先ほどご紹介したスレーブ受信部の上にシンクロソケットがあります。
そこにもう一つProfoto air remoteを用意してケーブルにつなげるか、シンクロコードでカメラのシンクロ接点と繋げれば同調して発光することが出来ます。air remoteは高価なので、もう一つ用意するとなると結構コストが掛かってしまうのが難点です。
シンクロコードはケーブルが増えてしまうのであまりオススメではないです。ただ、緊急避難的にシンクロケーブルも一本持っておくと、コマンダーが使えなかったときなどのリスクヘッジにはなると思います。
スタンド装着時のヘッドの振り

スタンド取り付け部分の構造上、普通のスタンドに取り付けるとProfoto D1は上の写真の角度までしか上に向けられません。
GODOX AD400は、ハンドルが干渉してしまうのですが、ハンドル部は取り外すことが出来るので真上に向けることも可能です。

逆に下向きの場合は、GODOXの場合は上の写真の角度までしか下に向けられません。
実際の撮影で、ストロボに何のアクセサリーも付けずに真下や真上に向けて使用することはあまり無いですが、ご参考までに。
気になった点
Profoto D1とGODOX AD400 Pro(AC電源で使用)を同時に使用中、両方とも半分くらいの出力で1秒に1シャッターくらいのペースで撮影していると、最初のうちはチャージスピードもほぼ一緒です。けれど10分くらいそのペースでの発光を続けていると、GODOX AD400 Proの方は熱対策の安全回路的なものが働くのか、チャージスピードが極端に遅くなります。その場合は、一度ストロボの電源をオフにすれば強制的にリセットできるのですが、ストロボにはかなり負担がかかりそうです。
Profoto D1の方はモデリングランプを点けっぱなしにしていると、モデリングランプが消えることはありますが、発光やチャージスピードに変化はありません。
AD400 Pro自体の使い勝手
バッテリー持ちは結構良いです。スタジオなどで長時間使用するときはオプションのAC電源を使っていて、バッテリーで使用するのは取材のときなどが主ですが、バッテリー1つでたいていの取材撮影は充分事足ります。
バッテリータイプのモノブロックストロボは初めてですが、チャージはフル発光でも1秒程度と早く、AC電源のものと遜色ないです。
取材時など、電源の場所を気にする必要もなく、設置の自由度が上がります。電源ケーブルが無いことで、セッティングのスピードも早くなり、電源の延長ケーブルも必要ないので荷物も減らせます。思っていた以上にケーブルレスの恩恵は大きいです。
LEDのモデリングランプはとても明るく、D1のモデリングランプと比べると時代の進歩を感じます。
TTL、HSS、先幕・後幕シンクロなど機能も盛りだくさんで、いろいろな場面で使えます。
400Wの大光量なので日中シンクロでも充分な光量が得られます。
まとめ
最初にAD400 Proを購入するときはそこまで期待していなかったのですが、良い意味で裏切られました。
そもそも比較するべきはProfoto D1ではなく、Profoto B1Xの方かと思います。ただD1と比べてみても、AD400 ProはAC電源タイプのストロボとして使用しても勝るとも劣らない性能です。バッテリータイプであるためD1との住み分けも出来るので、追加機材として持て余すこともありません。
オプションでProfotoやBroncolorのアクセサリ類を使用できるため、それらを揃えている場合も追加のストロボとして導入しやすいです。Bowensマウントも使用できるので、これから安価にアクセサリ類を揃えたい場合などは選択肢が豊富にあります。
D1と比べると一回りくらいコンパクトなので、バッグに収める際も省スペースです。外装のクオリティも高く、購入から2年弱経ちますが、故障なども特になくしっかりとした作りです。
クリップオンストロボを使っていたが、もう少し光量が必要で初めて大光量のモノブロックストロボを購入する。バッテリータイプのモノブロックストロボを使ってみたい。ソフトボックスなどの色々なアクセサリ類を使ってみたいなどの要求に対応できるので、幅広い方にオススメ出来るストロボです。







コメント
コメント一覧 (6件)
はじめまして。記事を大変興味深く読ませていただきました!
今b10を持っているのですがad300かad400の購入を検討しており、、疑問なのですがprofotoair remote(同じくttlなしのもの)はad400にも使えるのでしょうか?プロフォトとニ灯で使いたい時にどうされてるのかな、と思い質問させていただきました。お時間ある際ご返答いただけますと幸いです:)
コメントありがとうございます!
ProfotoとGODOXを混在させて使用するときですが、
1.ad400をスレーブモードにしてProfotoをair remoteで発光させてシンクロさせる。
2.記事内で紹介しているX2TというGODOXのコマンダーは上部にホットシューがあるので、X2Tをカメラにつけ、さらにその上にair remoteをつけて2段重ねで使用する。
3.ad400のシンクロソケットにもう一台air remoteをつけて、カメラにつけたair remoteで両方を発光させる。
僕の場合はこの3つの方法で使っています。
手っ取り早いのは1の方法で、安定するのは3かなという感じです。
1の場合は複数のセットを組んでいる場合などに他のストロボに反応して光ってしまいます。
2は何度か使ったてみたときに、たまに不発になるときがあって安定感がなかった印象です。ただ、両方のストロボの出力を手元で操作できる利点はあります。
3はair remoteをもう一台買うとなると値段がだいぶ高いので、微妙なところです…
長文になってしまいましたが、ご参考になれば幸いです!
ご丁寧にありがとうございます!誰に聞いてもわからなかったことなのでとても助かります。。
3のエアリモートを追加で買うのはやや厳しそうなので、
金銭的にはxt2を使用する2番がリアルかなぁと思いました。あのホットシューにprofotoリモートをつけ、そのままシャッターを切ればどちらもリンクして発光する、ただ発光に不安定要素がある、ということでしょうか?
ちなみに1のスレーブモードだと2台のストロボの向きにより反応したりしなかったりはする感じにはなりますよね、?
参考になったのでしたら、何よりです!
ちょっと気になったので2番の方法でテストしてみました。
追記に書いてみたので、よろしければ御覧ください。
2番の方法で安定していたので、オススメかと思います。
AD400に関してはスレーブの感度は良いほうだとは思いますが、仰っていただいたように向きとかで反応しないときもあります…
追記、追加動画拝見させていただきました!ご丁寧に本当にありがとうございます。。とっても助かりました:)
気に入っているストロボも購入できそうです。
これからもブログ見させていただきます。
ありがとうございました!
こちらこそ、コメント頂き勉強になりました!
お役に立てたようで良かったです。
ありがとうございました、遅筆なのでゆっくりですがブログ投稿していくので気が向いたらぜひ見て下さい!